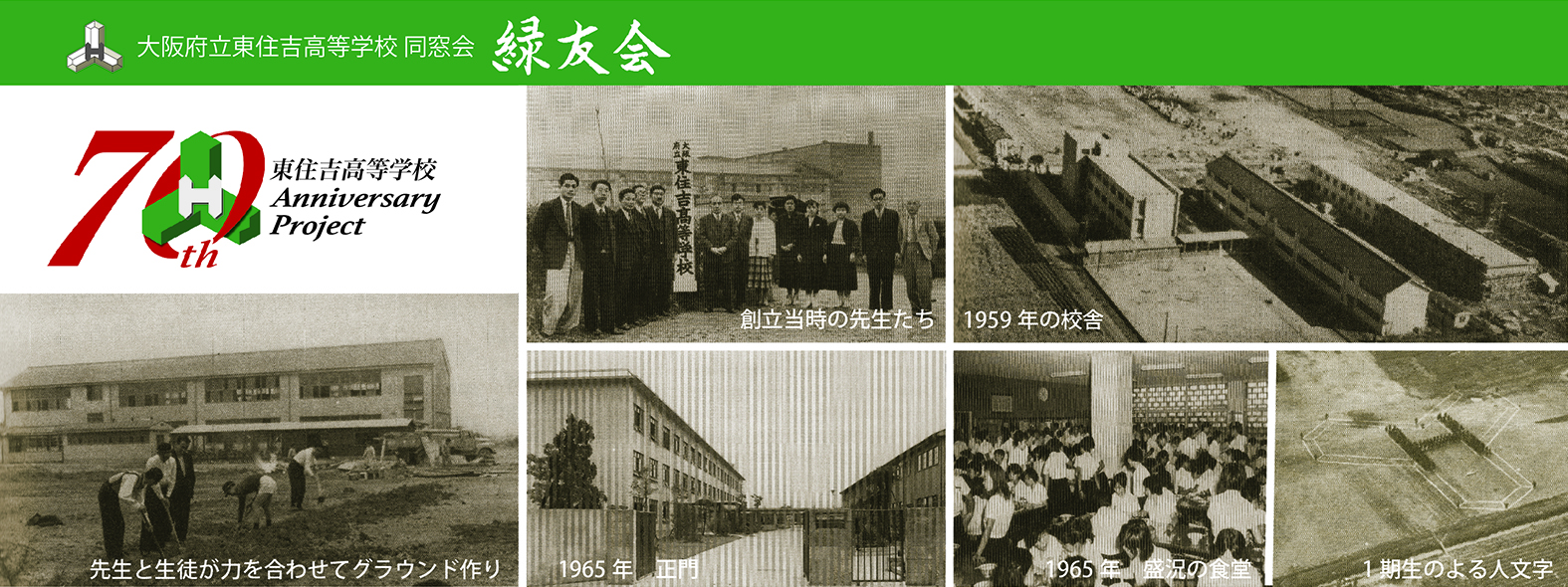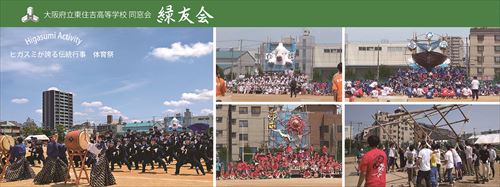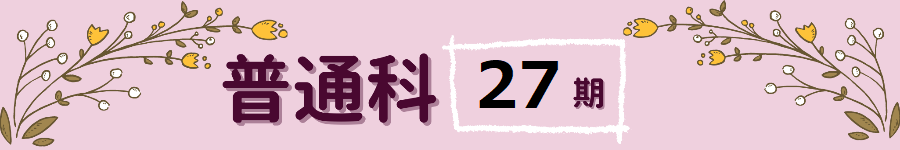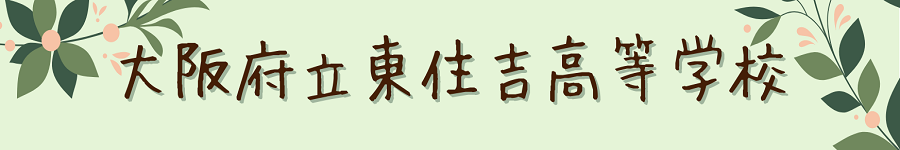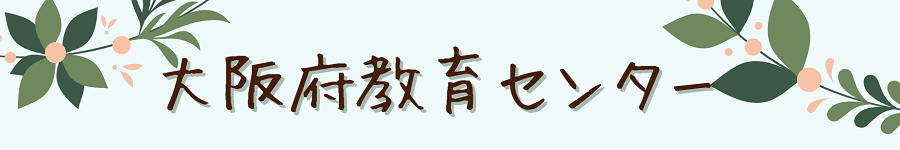(2023年3月20日)
怪、快、会則(名簿編)
緑友会長 川本正人(21期)
兵庫県尼崎市で、全市民46万人余りの個人情報が入ったUSBメモリーを紛失する事件があったのは昨年6月。委託業者がかばんに入れて持ち運んでいたときのことです。「怖いなあ」と他人事のように思っていましたが、その直後、会長に就任したばかりの私にも、緑友会事務局から1本のUSBが手渡されました。全会員約2万8,000人のデータが入った「名簿」です。私が保管して、時々上書きする際に持ってきてほしいとのことでした。
聞けば事務局スタッフも、もう1本あるUSBをヒヤヒヤしながら持ち帰り、自宅で事務処理の続きをしてきたとか。特に大変なのは、新卒会員のデータ入力。「紙」の申込書の内容をエクセル化していく作業です。定数が減ったとはいえ今も毎年300人分以上。それを長年、営々と……。ご労苦の詰まったUSBを手に、頭が下がりました。
とはいえ、このままではもちません。コロナ禍で電子化が一気に進んだ学校側に協力をお願いし、さっそく今春の卒業生から電子データによる申し込みに切り替えました。同時に「脱USB」を強く決意した次第です。
同じころ、衝撃の光景を事務局で目にしました。宛先不明で返ってきた大量の会報です。最近は年に約300通、以前は700通以上。毎年苦労して入力した数とほぼ同じだけの住所がこの時点で消去され、卒業生の3分の1が所在不明になっているそうです。
かつては会則で5年に1回の名簿作成が定められ、専門業者が冊子にしていました。しかし1997年の第9号(40期生まで収録)で中断。個人情報保護のためです。ハガキによる追跡調査もなくなりました。そして2013年、会則改正で「電磁的なデータとして作成し、事務局が保管する」となり、今に至っています。
でも、人の手による「電磁的」な作成・保管はもう限界。名簿の劣化は止められず、メールアドレスも集められません。そこで私たちは昨夏、様々な会員管理で使われている電子システムを調べました。対象は大阪、東京、兵庫の5社5製品。直接やオンラインの面談を繰り返し、確かめた機能は5点。「正確で判明率の高い名簿にする仕組み」「電子決済」「WEB総会」「ホームページとの連動」「電子名簿の閲覧と制限」です。すべてを満たしたのは1つだけ。しかも同窓会用に特化していて使いやすいうえ、最も安価でした。
9月の臨時役員会で導入を決め、すでに業者とシステムを構築中。でも費用は払っていません。総会での予算承認を得ていないからです。業者には「請求は、新年度6月の総会が終わってからに」と窮余のお願いを聞き入れてもらいました。
あとはみなさまから、「予算」と脱USBに必要な「会則改正」のご承認を得られれば本格スタートです。ご理解、なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m
※ 「同窓会システム」の概要は、6月お届けの会報でお伝えします。「マイページ」に関する大切なお知らせも同封しますので、必ずご確認ください。